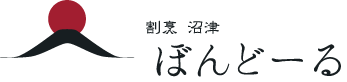�����������A
|
�����@���� Ryuji Isozaki |
�o���F��t���o�g�B���͌��u�Β��v�ɂĊ֍���莁�i���F���͌��u�����ˁv�X��i�~�V�������f�ړX�j�j�Ɏt���B�ɓ������u�Β��v�A����u�l��v���o�āA���˃��C�N�E�b�h�S���t�N���u�u�ΔȒ��v�ɂė������ƂȂ肻�̌�A���q�u���C���v���o�Č��݁A���B���Áu�ڂ�ǁ[��v�ɂė������߂�B
�����ւ̑z���F�u�̂���O�̐��E�͌��������̂ƌ��܂��Ă��܂��B���o�������邾���̗����Ȃ炿����Ƃ����H�v�����ł��\���܂���B�������A�����l�̐��E�͂����͂����܂���B���q�l�A�ЂƂ��l�ɂ����낪����A�o����闿���͂����������q�l�̂��������������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���ɓ�����Ƃł͗L��܂����A���͗����l�̐��E�͈ꐶ�C�s���Ǝv���A���q�l�ɖ������Ē�����悤�ɁA���㜍���Ċ撣���Ă܂���܂��B�v |
���H��^�@�`���X�Ǝp����i������{�̖��`
���{�����̑����_�ł���V�Ƒ��_�ɑ��������{�n�����߁A�`�P�����ɐ���K�ꂽ�̂́A���R���A�K�R���B�V�Ƒ��_�Ƃ��̐H���i��L����_�́A�R�C�̍K���L�x�Ȉɐ��������܂����B�C�ɂ��R�ɂ��b�܂ꂽ���{�́A�×�����H���ɂ��A���R�������܂����B�t�ďH�~���Ԓ������̐S�ŗ܂���B
�������A���{�̐H�������C��̕ω��Ȃǂɂ���āA���R�Ƌ��ɂ���킽�������̐H�͎p������A�X�ɐi�����Ă��܂��B����͕ω��łȂ��A�i���Ȃ̂ł��B
�V�̊��Ăł́u���ł��O�N�A�������N�A�Ă��ꐶ�v�ƌ�����悤�ɁA�ǂ������ł̏Ă��͓���A���̋Z�ʂ͒����C�Ƃɂ���ē�������̂ƂƂ���Ă��܂��B�`������邱�Ƃ́A�܂���葱���A���̏�Ői�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�{�̖����œK�ɁA�ŗǂɐH���Ƃ������Ƃ́A���{�l���|���Ă����u�`���v�Ȃ̂ł��傤�B
�g�y�s��̂������@�`���H����É������Â̊C�ƎR�̌b�݁`
�u�g�y�s��v�Ƃ́A�u�l�Ɠy�͓�ł͂Ȃ���̂ł���A�l�̖��ƌ��N�͐H�ו��Ŏx�����A�H�ו��͓y����Ă�B�̂ɁA�l�̖��ƌ��N�͂��̓y�Ƌ��ɂ���B�v�ƌ����Ă��܂��B
���{�͐H�Ǝ�������4�����x�ŁA�O���ɐH���ɗ������ŁA�����������҂̗~���͐V�����g�����h��ǂ��A�O����ꂽ���̂͂ǂ�ǂ�̂Ă��A�{��H�ו����̒m�b�̑�ȐH�����܂Ŏ����Ă����B�g�̂Ƒ�n�͈ꌳ��̂ł���A�l�����̎Y���ŁA�����n���G�߂ɂ͉A���̍앨���Ƃ�A�t�Ɋ����n���G�߂ɂ͗z���̍앨���Ƃ�܂��B��炷�y�n�ɂ����ď{�̕�����H���邱�ƂŁA�g�̂͊��ɒ��a����ƌ����Ă��܂��B
�ڂ�ǁ[��̂���É������ẤA�x�͘p�̊C�̍K�A�R�[�̑����ȋC��̎R�̍K�Ƃ������b�݂̕�ɂł��B���̎��R�Ƌ��ɐ����A�g�̂Ɏ�����邱�ƁA�܂��Ɏ��R�Ƌ��ɐ����邱�Ƃ́A�G�߂�厖�ɂ�����{�̔������̂ЂƂ�������܂���B
����ƁA�����ĂȂ��@�`��捂ȋ�ԂƁA�����ĂȂ��Ƃ����a�̑f���炵���`
�w�����ĂȂ����\�������\���Ȃ����^�Ӂ��^�S�x�U��̂Ȃ��S����̑Ή��͐S�ɋ����܂��B
�w����i���炢�j�x�͕�������A�n���̋V���̓��ɁA�Q�a�̕ꉮ����ћ��ɒ��x�𗧂āA���������邱�ƁB����ł͏���⒲�x�𐳌��A�ߕ��A���ՁA�[�߁A�d�z�ȂǁA�G�߂̂��̏�ɂӂ��킵��������Ƃ����Ӗ��B�G�߂�S�Ƒ̂Ŋ�����B
�C���⎼�x�A�J��������Ŏ��Ԃ�G�߂̕ω���g�̂Ŋ����A�G�߂̈ڂ�ς����܊��Ŋ�����邱�Ƃ��o���܂��B�����L���ȓ��{�l�͂��̋G�߂̈ڂ�䂭�l�������A�w����x�Ƃ�����Ԃɕ\�����Œ肵�܂����B
�w�����ĂȂ��x�����̐l�ւ̕\���ł���Ȃ�A�w����x�͎����ւ̕\���Ȃ̂�������܂���B���{�l�̂��ߍׂ₩�����琶�܂ꂽ�������ȕ�ƌ����܂��B
���{�l�Ȃ�m���Ă��������I���{�����̈Ⴂ������I
������
���ʂȋV���̎��łȂ�������A���{�����Ƃ��ďo�����͉̂��Η����ł��B
���Η����Ƃ́A�������ɓ��ꉷ�߂���x�ɁA�����Ƃ��̋�₦�邾���̗����Ƃ����Ӗ��ł��B���������x�ł��傤���B�ȒP�ȉ�ȗ����ł͂��̑��炸�`���I�ȕ������y���݁A���A�قǂقǂɖ����ł��āA���������l���Ŋy���ނɓK���ȗ����Ƃ������Ƃŕς���Ă����̂����Η����ł��B�H�ׂ�l�͗������y���ނ��Ƃɏd�_��������Ă��܂�����A�����ɂ��H�v���v��A�y����ň���H�ׂ��肵�āA�ޗ��ɂ��ᖡ���͂����悤�ɂȂ����̂ł��B
���i����
���i�Ƃ������t�������p��ł�����A�G�O���ďC�s�ɓO����Ƃ����Ӗ��������āA���L�����̂�����A�H�ׂ���̂������ނ͂��������g��Ȃ��Ƃ������̂ł��B
���̗����̂��Ƃ́A�z�O�i����j�i�������J���������T�t���i�����̐��i�������l�����̂��n�܂�ł��B�i�����ł́A��ʂ̐l�ɂ�������Ă��炨���ƁA�C�s�m���H�ׂĂ���̂Ɠ������i������H�ׂ����Ă���܂����A����͖{���ɂ悭�l����ꂽ�����ł��B�Ⴆ�A�����g���Ȃ��̂ň��₭�킢������ׂ�����A�������߂�ϊ������g���Ȃ��̂ŁA���z�⍪�ŏo�`���Ƃ��Ă��܂��B�{���̐��i�����́A�f�ނ̎�������������ϖ��킢�̂�����̂ł��B
��������
���������́A���i�����̈��Œ�������`����������ŁA�m�����p�̉����Ē��Ɍ��i�Ӂj�������Ƃ���Ăꂽ�����ł����A�����̗����Z�p�ɓ��{�����̋Z�p���a�������̂ŁA��������َq�Ɏn�܂��āA�����o�āA�����i���j�ɏI���Ƃ����������肪����܂��B
���ށi�����ۂ��j����
�����`���̗���������Ɏn�܂�A�̂��ɋ���_�n���ɍL�܂������̂̂悤�ł��B����͎�Ƃ��ċ��ނ������g���A��ɐ���ꂽ�������H��ɕ��ׂ���Ƃ������̂ŁA�������̍��ł͂��̐H��̂��Ƃ���ށi�����ۂ��j�Ƃ��������ŁA���ꂩ��t����ꂽ�������ƕ����Ă��܂��B����Ƃ��������������ɓ���܂��B
�{�V����
����́A�������Ղ̋V���̂Ƃ��̐����ȗ����ŁA��l���V�ɏ悹�Ă��o��������̂ł��B���ł͂قƂ�nj����܂���B�����I���Ώj�V�̉��ł��B�����ŏo�����̂��{�V�����ł��B���܂����`��������A�{�V�A��̑V�A�O�̑V�A�^�̑V�A����V�ȂǑV�̐��ŁA��`���؎O�`��Ȃǂ����߁A�V�ɏ悹����i�������낢��ł����A�ō����̖{�V�ɕς�肠��܂���B�V�ɂ͈����o�����t���܂��B���x�e������A�����Ƃ��َq���o���A���ɂ܂������������悤�Ȃ�y����ȗ������������܂��B���������{�V�������u�����i�������傤�j�����v�Ƃ����܂��B
���B�̈Ӗ�
���B�̊��i�����j�ƖB�i�ɂ�j����{�Ƃ���ӂŁA�ޗ��ƋZ�p�����������̎��ŁA���̌���{�����Ƃ������t���ł��܂����B���{���������i�����ȂǓ���ȗ����������A�����Ԃ�ɂ���ĕω����A�͎̂ς�ƏĂ��̓�{���Ă������o���_����l����A�O������g����Ƃ��������@������ޗ��������A�����ɖ��o�̕��A�y���ݕ����ł��A����ɐ��m�����⒆�ؗ�������q���g��������ĉ���������u�������v����\�I�Ȃ��̂ł��B
��ȗ���
�u���������v�Ƃ����Ή�Ȃ������ƊԈ���₷���̂ł����A�{���A��ȗ����Ƃ����܂��̂́A�o���A�̂̉�ȂǂŁA���̍���x�Ɍy�����o�����������̂��ƂŁA������c��܂��͓̂�̎��Ƃ�����̐Ȃł̗����ł��B��ȗ����ɂ́A���̂Ȃ��V���^��A���̏�ɗႦ�Ό����ɑ�̑���A���g�A�ɒB���A�C�V�Ȃǂ̏������A�Ō�͉ʕ���₽�����́A�Â����̂��o�܂��B���݂͉�Ђ̉���̎��̗������A��ȗ����Ƃ����̂������ł����A��Ȃ��������܂������ʂ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
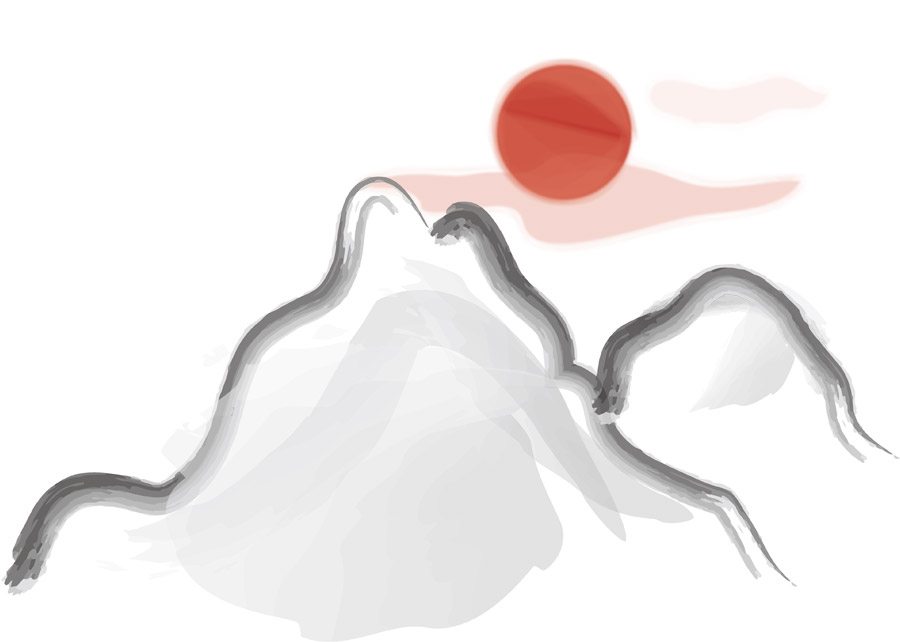
���\��E���₢���킹
���B���Âڂ�ǁ[��@TEL:055-925-2511�@��410-0022�@�É������Îs�剪2870-2
�c�Ǝ��ԁ@11:00�`14:00/17:00�`20:00�@���j��x��